【Googleフォトだけ消したい】注意点あり!スマホの写真を残す方法。Googleドライブで補う方法も
今回はGoogleフォトのバックアップのみを削除する方法についてシェアさせていただきます。 また、その後の運用方法やGoogleフォトのややこしい削除の仕様を回避するためにGoogleドライブを使ったシンプルな写真のバッ…
スマホで生活が変わる!皆さんに実感いただけるよう「スマホのコンシェルジュ」がお手伝いします!
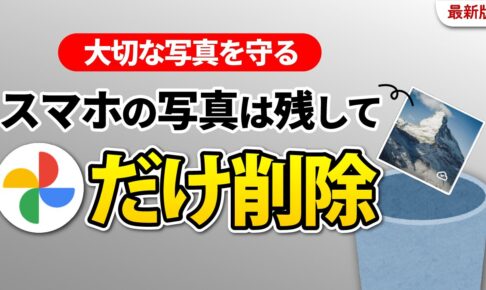
今回はGoogleフォトのバックアップのみを削除する方法についてシェアさせていただきます。 また、その後の運用方法やGoogleフォトのややこしい削除の仕様を回避するためにGoogleドライブを使ったシンプルな写真のバッ…
今回は、「意外と知らない!スマホのスキャンはどの方法が一番便利!影の消去・送信で差が出る!」について説明して参ります。 日常生活でも、お知らせや案内等、いろいろなものが紙でおくられてくるかと思います。 紙のまま保管して、…
今回は、「Gmail・Googleフォトの放置は危険!クリーンアップ機能で簡単メンテナンス」について説明して参ります。 「Gmail」「Googleフォト」のサービスを利用していると、メールの受信はもちろんですが、写真や…
今回は、「写真や動画の整理 iCloud・Googleフォトにある写真や動画をパソコンやスマホに取り出す方法」について説明して参ります。 使える環境で、写真や動画を整理する為の最適な方法が変わりますので、その点についても…
今回は、「大事なデータの保存先 どこが一番安全!」について説明して参ります。 最近は、紙の節約や資源の効率化で、デジタル化したデータを使用する機会も増えてきています。 また、撮った写真も、以前はプリントして確認をしていま…
今回は、このGoogleドライブが一体なんなのか、という点を皆様と確認していきたいと思います。 <動画内容>1. Googleドライブとは2. 利用するメリット3. Googleフォトとの違い4. 画面構成5. データを…
今回は、「スマホに保存した写真をPDFにするならどうする?保存した写真をPDFにする方法」について説明して参ります。 スマホで撮った写真やスクリーンショットをPDFにする場合には、複数のやり方があります。 「Google…
今回は、Googleの発表に対する対処方法やSNS等で放置してしまっているアカウントの削除などについてみていきたいと思います。 <動画内容>1. 無効なGoogleアカウントに関するポリシー変更について2. 2年間操作の…
今回は、「知らないと損する!「共有方法」で通信量と手間が半分になる!クラウドの正しい使い方」について説明して参ります。 「クラウド」をうまく使うと、手間と通信量を半分にする事が出来ます。 「写真」「動画」「ファイル」等が…
2021年5月末に終了したGoogleフォトの無料・無制限バックアップサービス。 実はこの保存容量の上限はGoogleドライブ、Gmail、Googleフォトの合計だということをご存知ですか? そこで今回は、無料プランの…