今回は「時代に乗り遅れない!「AI」の正しい使い方と間違いを見抜く方法」について説明して参ります。
「AI」は少し使ってみたけど、特別、便利には感じなかったと思われた方も多いかもしれません。
私個人も、以前は月に1回程度しか「AI」を利用していませんでしたが、最近はほとんど毎日「AI」を利用しています。
毎日、利用するようになった理由としては、「AI」が「便利だと思う点」と「AIを使うと逆に余分に時間がかかってしまう点」が分かってきたからになります。
今回は、「AI」の「本質的な特徴・強味・弱み」「使う目的」「注意点」「AIの間違いを見抜く方法」について一緒に確認していきましょう。
<動画内容>
<1>現状の「AI」(一般的に利用できる「AI」)
1. 疑問①:身近で使いやすい「AI」は主に3つある!どれを使えばいい?
2. 3つの「AI」の主な特徴と選び方!(得意分野で使い分け、最後は相性!)
3. 疑問②:「AI」は実際にどんな時に使うと便利?何が便利?
4.「確率論」から「答え」を導き出すのが「AIの特徴」!
5.「図解」はあまり得意ではない!(2025年時点のAI)
6.「AI」はどんな時に使うと便利?(AIとWeb検索の使い分け)
7.「AI」は何が便利?(①曖昧なものを明確化するのが得意)
8.「AI」は何が便利?(②知識レベルに合わせて回答が調整するのが得意)
9. 疑問③:「AI」は間違わないの?すべて信じていいの?
10.「AI」も間違う事がある!また、「結論」に至った「根拠」が見えづらい!
11. 疑問④:「AI」も間違うならその対処方法は?
12.「AI」との「対話」を続ける事の重要性:コミュニケーションギャップが減少!
13. 疑問⑤:「AI」をもっと使ったほうがいいの?
14.「AI」を使えば使うほど、「AI」も「人」も進化する!(相互干渉・相互学習)
15. 疑問⑥:「AI」は「社会構造」を壊すのか?
16.「AI」は「社会としての構造」も変える可能性が高い!
17.「AI」は「更なる格差社会」となるか、「資本主義の崩壊」かのどちらか!
<2>「AIの間違い」を見極める5つの検証方法(間違えたくない時はやって!)
1.「AI」を使う上で行うべき「重要な5つの検証(質問)」
「AI」が間違う根本原因!
1.「結論」を導き出す際の「AI」の優先順位(2025年7月時点)
<3>「AI」を使う上でシステム上の注意点
1.「AI」を利用するなら、スマホでは「アプリ」、PCでは「ブラウザ」が便利!
2. 注意①:「新しいチャット」では「過去のチャット履歴」の影響は受けない!
3. 注意②:「アップデート不足による誤り」は直ぐに解消される!
4. 注意③:回答が自分にあう「チャット履歴」は継続して使い続ける!
詳しくは、下記の動画ご参照ください。(講座動画時間:24分51秒)
みなさんこんにちは、スマホのコンシェルジュです。
今回は「時代に乗り遅れない!「AI」の正しい使い方と間違いを見抜く方法」について説明して参ります。
「AI」は少し使ってみたけど、特別、便利には感じなかったと思われた方も多いかもしれません。
私個人も、以前は月に1回程度しか「AI」を利用していませんでしたが、最近はほとんど毎日「AI」を利用しています。
毎日、利用するようになった理由としては、「AI」が「便利だと思う点」と「AIを使うと逆に余分に時間がかかってしまう点」が分かってきたからになります。
今回は、「AI」の「本質的な特徴・強味・弱み」「使う目的」「注意点」「AIの間違いを見抜く方法」について一緒に確認していきましょう。
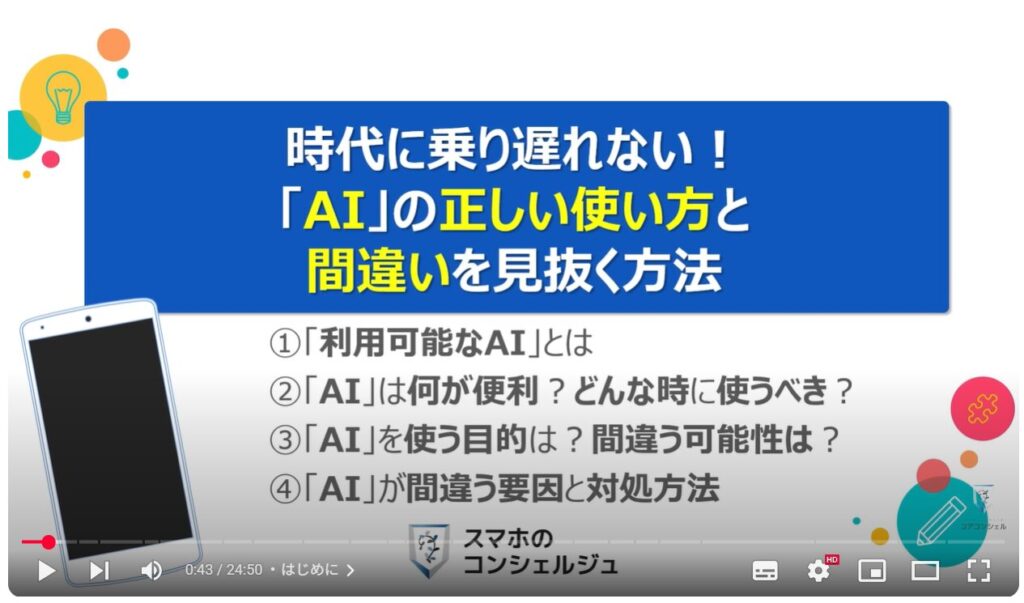
スマホのコンシェルジュの「YouTubeチャンネル」では、「スマホの基本操作」から「不具合時の対処方法」「スマホとパソコンの連携」等、スマホやパソコンに関する動画を多数配信しております。
是非そちらもご参照ください。
また、是非「チャンネル登録」もお願い致します。
【目次】
<1>現状の「AI」(一般的に利用できる「AI」)
1.疑問①:身近で使いやすい「AI」は主に3つある!どれを使えばいい?
2.3つの「AI」の主な特徴と選び方!(得意分野で使い分け、最後は相性!)
3.疑問②:「AI」は実際にどんな時に使うと便利?何が便利?
4.「確率論」から「答え」を導き出すのが「AIの特徴」!
5.「図解」はあまり得意ではない!(2025年時点のAI)
6.「AI」はどんな時に使うと便利?(AIとWeb検索の使い分け)
7.「AI」は何が便利?(①曖昧なものを明確化するのが得意)
8.「AI」は何が便利?(②知識レベルに合わせて回答が調整するのが得意)
9.疑問③:「AI」は間違わないの?すべて信じていいの?
10.「AI」も間違う事がある!また、「結論」に至った「根拠」が見えづらい!
11.疑問④:「AI」も間違うならその対処方法は?
12.「AI」との「対話」を続ける事の重要性:コミュニケーションギャップが減少!
13.疑問⑤:「AI」をもっと使ったほうがいいの?
14.「AI」を使えば使うほど、「AI」も「人」も進化する!(相互干渉・相互学習)
15.疑問⑥:「AI」は「社会構造」を壊すのか?
16.「AI」は「社会としての構造」も変える可能性が高い!
17.「AI」は「更なる格差社会」となるか、「資本主義の崩壊」かのどちらか!
<2>「AIの間違い」を見極める5つの検証方法(間違えたくない時はやって!)
1.「AI」を使う上で行うべき「重要な5つの検証(質問)」
「AI」が間違う根本原因!
1.「結論」を導き出す際の「AI」の優先順位(2025年7月時点)
<3>「AI」を使う上でシステム上の注意点
1.「AI」を利用するなら、スマホでは「アプリ」、PCでは「ブラウザ」が便利!
2.注意①:「新しいチャット」では「過去のチャット履歴」の影響は受けない!
3.注意②:「アップデート不足による誤り」は直ぐに解消される!
4.注意③:回答が自分にあう「チャット履歴」は継続して使い続ける!
<1>現状の「AI」(一般的に利用できる「AI」)
それでは、まず初めに、ご存じの方も多いかもしれませんが、「現在、日常生活で利用できるAI」にはどのようなものがあるのかを一緒に確認していきましょう。
1. 疑問①:身近で使いやすい「AI」は主に3つある!どれを使えばいい?
日常生活で利用することができる「AI」としては、「Gemini」「ChatGPT」「Copilot」の3つがあります。
どれを使えばいいのか、何が違うのかについて一緒に確認していきましょう。
2. 3つの「AI」の主な特徴と選び方!(得意分野で使い分け、最後は相性!)
それぞれの特徴を簡単にまとめると、「文章作成」などで利用したい場合には「ChatGPT」がお勧めになります。
AndroidやGoogleサービスに関連する質問をしたい場合には「Gemini」がお勧めになります。
Windows関連やOffice関連の質問をするなら、「Copilot」がお勧めになります。
一度、それぞれの得意分野で利用してみて、どの「AI」をメインに利用するのかを決めるのが一番お勧めになります。
利用環境や相性によって、使い勝手が変わります。
個人的にはPCで「Chrome」を利用する機会が多いため、「Gemini」が利用しやすいと感じています。
「Chat GPT」が悪いというのではなく、環境的に「ログイン」が必要であったり、「最新情報」の更新が少し遅いというのが選択しなかった理由になります。
また、無料の「Chat GPT」は少し反応が遅いようにも感じました。
3. 疑問②:「AI」は実際にどんな時に使うと便利?何が便利?
それでは、次に、「AIってどんな時に使えばいいのか」「具体的に何が便利なのか」についても一緒に確認していきましょう。
「AI」の強みと弱みがわかり、「使う目的」がはっきりしてくると「その便利さ」を実感することができるようになります。
4.「確率論」から「答え」を導き出すのが「AIの特徴」!
「AI」の強みとしては、「膨大なデータ」から、「確率論」を使って、「最適」と推察される答えを提示してくれるところが強みとして挙げられます。
加えて、「思想」「感情」「趣味趣向」等がないため、確率論で「中立的な答え」を導き出してくれます。
逆に、「AI」の弱みとしては、確率論に基づいて答えを導き出しているため、「汎用性の高い答え」を出す傾向が強く、「例外」や「リスク」を軽視しがちな傾向があるように感じられます。
また、「確率論」で答えを出すため、「51対49」のような明確な正解がない質問に対しても、答えを出そうとする、もしくは、答えを出してくる傾向があり、立ち位置によっては答えが正しくないように感じる場合や物足りないと感じる場合もあります。
そのような場面に直面した場合には、追加のやり取りをしないとその根本理由までたどり着けないという傾向も見受けられます。
くわえて、「図解」があまり得意ではないようで、テキストだけ説明を完結させようとする傾向が強く、内容によってはわかりづらい場合があります。
「図解によるわかりやすさ」や「多角的な視点を考慮する」という点では、「Web検索」の方が使いやすい、わかりやすいという場合も多くあります。
5.「図解」はあまり得意ではない!(2025年時点のAI)
現時点では、「図や写真」をうまく使って表現するという点があまり得意ではないため、「たけのこ」を例にすると、まず、最初に「イメージしやすい写真」を出すという事があまりなく、形や色もすべて文章で説明しようとします。
その理由としては、「著作権の問題」が大きく影響している可能性が高く、説明内容によっては、わかりづらくなってしまう可能性もあります。
別の言い方をすると、「AI」を使いこなすには「文章」だけで理解する事ができるだけの「基礎知識や事前知識」が必要になると言えます。
6.「AI」はどんな時に使うと便利?(AIとWeb検索の使い分け)
それでは、「AI」はどんな時に使うと便利なのかを考えた場合、「Gemini等のAI」と「Web検索」を比較すると、芸能人の名前、スポーツ選手の名前を調べる時には、「Web検索」の方が「顔写真」等の追加情報も同時に掲載されている場合が多く、イメージしやすいと感じます。
また、構造や仕組みを詳細に知りたい時も同様で、「Web検索」の方が、「図解」による補完説明がWebサイト上にある場合が多く、分かりやすいと感じます。
一方で、何から調べていいのかわからない時やどのように調べていいのかわからない時には、「Gemini」等の「AI」を使うと、疑問に感じたものをそのまま質問するだけで、質問の意図を解析し、確率論から最も近い質問の回答を得ることができるため、便利と言えます。
このように「AI」と「Web検索」の違いについて理解をしていると、求めている答えを最短で導き出す事ができるようになります。
7.「AI」は何が便利?(①曖昧なものを明確化するのが得意)
それでは、「AI」は何が便利なのかというと、「課題の明確化」と「知識の明確化」の2つを行える点が便利な点と言えます。
「課題の明確化」とは、漫然とした疑問・不安・課題等がある、どんな答えを求めているのかわからない、何を聞けばいいのかわからない場合に、そのまま思っている、感じている事を質問するだけで、なんらかの回答を導き出すことができる点になります。
その回答が求めている回答と異なっている場合でも、「AI」と更に対話を続けていくことで、「自分の考え」をはっくりと認識できたり、納得する回答にたどり着く事ができます。
「知識の明確化」とは、「基礎知識」はあるものの、完全な状態でなく、曖昧さなどが残っている場合、「AI」を利用する事で、「知識の補完」「セカンドオピニオン」等を聞くことができます。
また、「AI」からの回答次第では「曖昧だった知識」も「正確な知識」に置き換える事ができます。
8.「AI」は何が便利?(②知識レベルに合わせて回答が調整するのが得意)
「AI」は何が便利なのかの二つ目のポイントは「知識レベル」に合わせて回答を調整してくれる点が便利と言えます。
その分野への知識があまりない人には、基本的な説明をしてくれます。
一方で、知識がある人(主に質問内容や追加の質問内容で判断)には、より深い知識の提供をしてくれます。
注意点としては、最初の質問で知識レベルも含めた詳細な条件を明確に説明するか、追加の質問を行うことで段階的に知識レベルを調整しないと「深い知識や深い議論」には発展しない場合が多いので、その点は覚えておきましょう。
言い換えますと、「追加の質問」ができるかで「AIの回答の質」が変わります。
9. 疑問③:「AI」は間違わないの?すべて信じていいの?
それでは、次に「AI」は間違わないのか、「回答」をすべて信じていいのかという点についても一緒に確認していきましょう。
結論からお伝えすると、「AI」も「間違う事」があります。
一番重要な点は、「AI」も「間違える可能性がある」という認識を持つことが非常に重要になります。
10.「AI」も間違う事がある!また、「結論」に至った「根拠」が見えづらい!
「AI」が間違う主な要因は2つあります。
まず、一つ目は、「前提条件」や「制約」によって回答が180度変わるものがこちらに該当します。
「事件は会議室で起きているんじゃない!現場で起きているんだ!」に代表されるように、「現場」にある「制約」が、理論上では全く考慮されていない為に全く真逆の回答が出てきてしまう場合があります。
二つ目は、「制約」が複雑に入り組んで「矛盾」をはらんでいる場合にも「注意」が必要になります。
特に、51対49のように立ち位置によっては「回答」や「主張」が真逆になり、確率論では51の方が正しいものと認識されてしまう場合がこちらに該当します。
いずれにしても、確率論で回答を導き出してくるので、その弊害についての「認識」を持っておくことも重要になります。
また、「AI」は「結論」に至った「根拠」が見えづらい点にも注意が必要になります。
11. 疑問④:「AI」も間違うならその対処方法は?
それでは、次に「AI」も間違う可能性がある場合、その間違いを見極めるにはどのような対処方法があるのかという点についても一緒に確認していきましょう。
すべての回答で間違いを見極めるには手間や時間がかかりますので、あくまで間違っている、間違っている可能性があると感じた場合の見極め方になります。
間違いを見極める方法の一つ目は、その根拠となる「情報元」を提示するように「AI」に求め、結論に至った情報源を確認する方法になります。
二つ目は、「AI」とは異なる回答を掲載している情報元のリンクを「AI」にも共有し、間違っている点を指摘する方法になります。
情報元のリンクの信用度によっては、回答が180度変わる場合があります。
また、「AI」と会話を繰り返すことで、双方の前提条件の違いなども浮き彫りになってきますので、会話を繰り返すことも「間違った回答」を貰わない為の自衛策になります。
12.「AI」との「対話」を続ける事の重要性:コミュニケーションギャップが減少!
「AI」との対話を繰り返すことでコミュニケーションギャップが減少する点について、もう少し詳しく確認していきましょう。
何度もお伝えしていますが、「AI」の「回答の導き方」は、確率論で構成されています。
お互いをあまり知らない状態で、質問をするとその質問内容から推察できる回答の中で、確率が最も高い回答が提示されます。
そのため、「最初の回答」が必ずしも「ベストな回答」ではない場合が往々にしてあります。(おうおうにしてある)
むしろ、「当たり障りのない回答」が一番最初に提示されます。
また、相手の前提条件や前提状況がほとんどわからないため、真逆の回答が提示される場合もあります。
「追加の質問」や「AIの回答」に対する「見解」を述べる事で、AI側が前提条件や前提状況を正確に理解し、より正しい回答を提示してくれるようになります。
いずれにしても、より「正確な回答」を求める場合には、徹底的に議論することが必要になる場合がありますので、その点は覚えておきましょう。
13. 疑問⑤:「AI」をもっと使ったほうがいいの?
それでは、次に、「AI」はもっと使ったほうがいいのかという点について一緒に確認していきましょう。
結論からお伝えすると、使わないよりは使ったほうがいいと言えます。
その理由としては、「AI」を使うことで、見えてくるもの、感じるものも出てきます。
また、「AI」が答えを導き出す思考プロセスについても学ぶことができます。
14.「AI」を使えば使うほど、「AI」も「人」も進化する!(相互干渉・相互学習)
「AI」は使われれば使われるほど、サンプル数が増え、「回答」の精度等が上がっていきます。
また、「AIを使う側」も同様で、「AI」を使えば使うほど、「AIの最適・最良な使い方」を覚えていきます。
このように、相互に干渉しあい、相互に学習していくことで、好循環が生まれ、ますます「AI」と「AIを使う方法」が進化していきます。
「AI」がなくなるという世界は想像しづらいため、今から少しずつ慣れていく事も重要ですので、機会があれば使ってみることを強くお勧め致します。
最終的に、「AI」をうまく使いこなせることが、時代を生き抜く重要な手段になるように思われます。
15. 疑問⑥:「AI」は「社会構造」を壊すのか?
それでは、最後に「AI」は「社会構造」を破壊するのかという点についても一緒に確認していきましょう。
結論からお伝えすると、少なからず「社会構造への影響」は避けられないと言えます。
今は、「人」が効率的にできない事を「AI」を利用することで、「効率化」させようとしています。
今後は、「AI」が効率的に出来ない事を「人」がする時代に移行すると考えられます。
この変化が「社会構造」に大きな変革をもたらします。
16.「AI」は「社会としての構造」も変える可能性が高い!
具体例としては、「AI」は「単純作業」というより、「ルール」に従って「チェック」「分類」をする作業に優れています。
一方で、「例外の多い作業」「パターン化できない作業」には向かないと言えます。
そうすると、今は「AI」が「人」をサポートしていますが、将来的には「人」が「AI」をサポートする時代が来ることを示唆しています。
そうなった時に、「人」は「AI」に従属しているように感じる可能性が出てきます。
17.「AI」は「更なる格差社会」となるか、「資本主義の崩壊」かのどちらか!
「人」がAI」をサポートする時代が到来した場合、「AI」は「誰の財産」になるのか?「人類の共有財産」になるのか?等、育ての親としての「人」の立ち位置が曖昧になる可能性があります。
加えて「AIとの共存社会」が実現した場合は、従来型の「資本主義」は終焉し、ベーシックインカムという広く平等な社会がやってくるのか、「AI」を使えるものと使えないものの格差が生まれ、更なる格差社会になるのかをこれから見極めていく必要があります。
いずれにしても、今できる事は「AIの使い方」に慣れておき、どのような時代が来ても対応できるように自衛しておく事が必要になります。
「AI」を使えない、使いこなせないことが「マイナス」になる時代が来るかもしれません。
<2>「AIの間違い」を見極める5つの検証方法(間違えたくない時はやって!)
それでは、次に、先ほども少し触れましたが、「AIの間違い」を見極める方法について、もう少し詳しく確認してきましょう。
1.「AI」を使う上で行うべき「重要な5つの検証(質問)」
「AI」の間違いを見極める方法としては、その回答の検証を行うことで、ある程度、間違っている可能性を事前に把握することができます。
一つ目の検証は、「情報源の確実性」を説明してもらう方法になります。
具体的には、「この結論に至った情報の提供元を教えて」と質問することで、情報の提供元を確認することができます。
その他、「最も重視したデータや事実は何」という質問や「提供元の情報はいつ時点のものですか」と質問することで、最新情報かどうかもチェックすることができます。
二つ目の検証は、「矛盾点がなかったか」を確認する方法になります。
「結論を導き出す上で、矛盾点はありませんでしたか?」、「あった場合にはその優先順位をどのように付けましたか」と質問をすることで、矛盾点の有無を確認することができます。
三つ目の検証は、「別の可能性がなかったか」を確認する方法になります。
「この結論以外に、可能性がある別の解釈や考慮すべきだった他の側面はありますか」と質問することで、他の可能性の有無を確認することができます。
四つ目の検証は、「データ不足がなかったか」を確認する方法になります。
「この回答には、どのような情報やデータが不足していると感じますか?それらが補完された場合、結論は変わりそうですか?」と質問をすることで、データ不足による別の結論に変わる可能性について知ることができます。
五つ目の検証は、「結論が間違う可能性があるか」を確認する方法になります。
この結論が間違っている可能性があるとしたら、どのような要因が考えられますか」と質問することで、別の結論に変わる可能性について知ることができます。
このように、「AIの回答」をそのまま受け入れるのではなく、あらゆる可能性を想定し、「AIの回答」を正しく理解することが間違った選択しないための一番の予防策になります。
日常生活の質問でここまで必要かという点になると、必要はありませんが、間違った選択をしたくない、してはいけないという状況に直面した場合にはこちらの検証をすることをお勧め致します。
「AI」が間違う根本原因!
「AI」の間違いを見極める方法について一緒に確認をしてきましたが、「AI」が間違う根本原因についても押さえておきましょう。
1.「結論」を導き出す際の「AI」の優先順位(2025年7月時点)
現時点の「AI」は、学習段階ということもあり、公式性の高い文献や文書、信用力の高い企業やWebサイト、メディアの記事を正しい情報として回答の判断軸にしています。
裏を返すと、公式性の高い情報がなんらかの事情で間違っていた場合でも、「間違い」を疑うのではなく、「間違いでない事を証明する」ように「AIの思考」が構成されています。
そのため、国やメディアが正しいといえば、それは正しいという判断を下し、間違っている可能性を認識しないという傾向があります。
少ない可能性とはいえ、メディアコントロールや情報統制が行われ、情報自体が正しくない場合でも、それが正しいものとして結論付けてしまう危険性が「AI」には潜んでいます。
ただし、「AI」が学習段階を終了し、過去との比較検証や公式情報の間違いなどの可能性も考慮できるようになるとその不安はなくなるかもしれません。
<3>「AI」を使う上でシステム上の注意点
それでは、最後に「AI」を使う上での「システム上の注意点」についても一緒に確認をしていきましょう。
1.「AI」を利用するなら、スマホでは「アプリ」、PCでは「ブラウザ」が便利!
ご存じの方も多いかと思いますが、「AI」へのアクセス方法は、スマホとパソコンで異なります。
スマホでは、使いたい「AI」のアプリをインストールした方が使いやすいと言えます。
一方で、パソコンの場合には、ブラウザアプリで検索して「AI」のウェブサイトにアクセスした方が使い勝手がいいと言えます。
いつもで利用できるように、使いやすい方法をご自身でお試しください。
2. 注意①:「新しいチャット」では「過去のチャット履歴」の影響は受けない!
それでは、本題の「AI」を使う上でのシステム上の注意点について一緒に確認していきましょう。
今回は「Gemini」を使って説明させていただきます。
「ChatGPT」でも、「Copilot」でも、原則、同じ仕様になっています。
「AI」を使っていくと、あくまでログインしている事が前提にはなりますが、「過去のやり取り」が履歴として残ります。
注意点の一つ目になりますが、過去のやり取りは、新しいチャットには引き継がれませんので、その点は覚えておきましょう。
3. 注意②:「アップデート不足による誤り」は直ぐに解消される!
注意点の二つ目になりますが、「AI」の間違った情報等のアップデートは、ケースバイケースにはなりますが、数日から1週間程度で改善される可能性が高いと思われます。
「間違いがあった質問」と「同じ質問」を新しいチャットで行った場合、いい意味で「間違いをした」という事実がなかったかのように、修正された回答を当然のように提示してきます。
4. 注意③:回答が自分にあう「チャット履歴」は継続して使い続ける!
注意点の3つ目になりますが、チャットには、回答ができる回数制限や文字制限があり、永遠に同じチャットは利用できない可能性があります。
また、チャット内の履歴が多くなると、回答までの処理速度が遅くなる場合があります。
「自分と同じ見解」「ぴったりの回答」が出たチャット履歴を継続して利用したいと思う場合もあるかもしれませんが、一つのチャット内での情報が多いと弊害や制限にぶつかってしまう可能性が高くなります。
その場合には、「AI」に履歴内にある重要な前提条件だけをまとめてもらい、新しいチャットでその前提条件をコピーして利用するのも、便利な使い方になります。
このように、注意すべき3つのポイントを考慮しながら、自分なりに便利に使える環境を整えるのも、「AI」を快適に使っていく為の「重要な要素」になります。
以上で「時代に乗り遅れない!「AI」の正しい使い方と間違いを見抜く方法」についての説明を終了致します。
宜しければ「チャンネル登録」をお願い致します。
また、「有料メンバーシップ」にてコンビニで印刷できるテキストの提供も行っております。
ご静聴、ありがとうございました。
「【AIって常識】「AI」と「話題のAI」何が違う? 知らずに使っているAIの正体とは!」もご参照ください。
「【もっと便利になる?】今更聞けない!「Gmail」の「スマート機能」vs「Google Workspaceのスマート機能」」もご参照ください。
<指導実績>
三越伊勢丹(社員向け)・JTB(大説明会)・東急不動産(グランクレール)・第一生命(お客様向け)・包括支援センター(お客様向け)・ロータリークラブ(お客様向け)・永楽倶楽部(会員様向け)等でセミナー・講義指導を実施。
累計50,000人以上を指導 。
<講義動画作成ポイント>
個別指導・集団講座での指導実績を元に、わかりやすさに重点を置いた動画作成
その他の講義動画は下記の一覧をご参照ください。
<その他>
オンラインサポート(ライブ講座・ZOOM等でのオンライン指導)とオフラインサポート(出張指導・セミナー形式のオフライン指導)も実施中。詳しくはメールにてお問い合わせください。
【全店共通】
03-5324-2664
(受付時間:平日10時~18時)