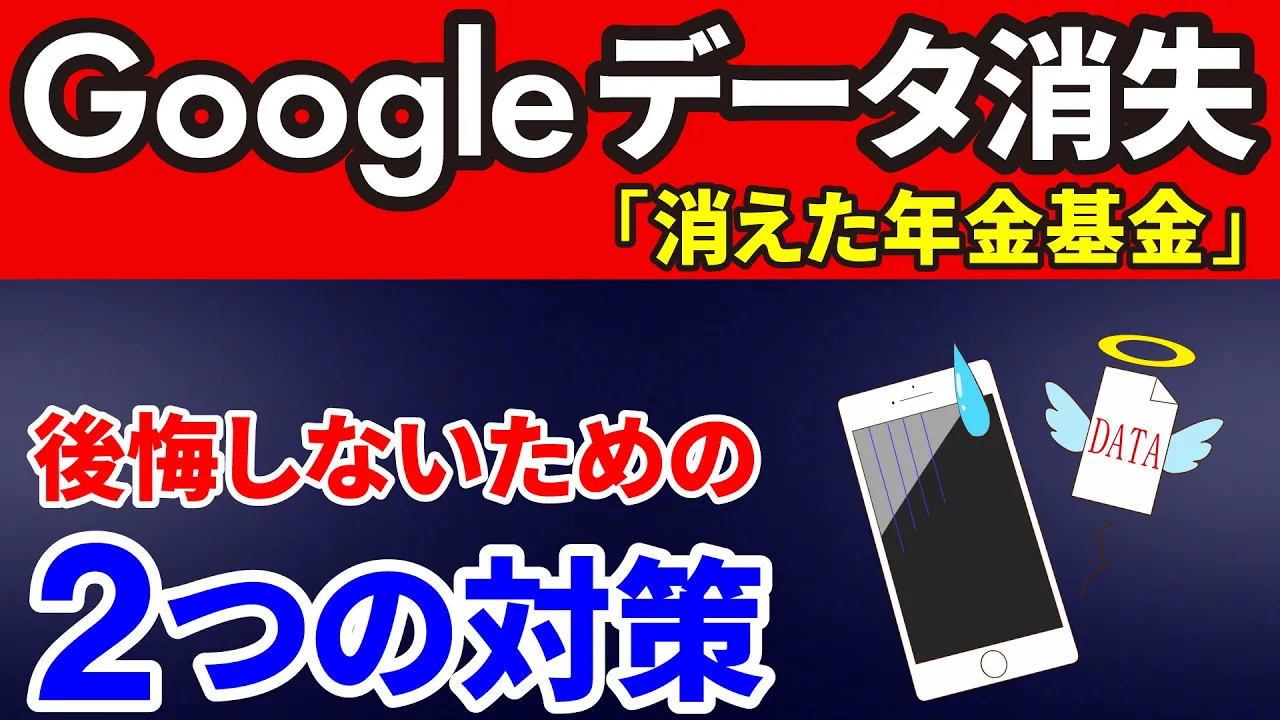今回は、「Googleでデータ消失!年金基金のデータが消えた理由と個人でもすべき安全対策」について説明して参ります。
豪州の年金基金のデータが消えた要因は、Google側の人為的なミスで発生したものになります。
但し、データ自体が消えてしまい、復旧までに1週間かかったという事件になります。
また、そのデータ復旧にGoogle以外のバックアップデータが活用され、最終的に1週間で復旧する事が出来たという事例でもあります。
この事件から、「Googleフォト」等に保存している写真やデータが安全なのか、個人でも出来る安全対策はあるのかについて一緒に確認していきましょう。
<動画内容>
<1>データを保存する「オンラインストレージ」とは
1. データを保存する「オンラインストレージ」とは?(バックアップを含む)
2.「オンラインストレージ」の5つの特徴
3.「オンラインストレージ」の4つの危険性
<2>「オーストラリアの年金基金」で発生した「データ消失」の原因とは
1.「年金運用の契約者」がアカウントに1週間アクセス出来ない事件が発生!
2. 原因は「人為的なミス」!「契約サービス」が自動的に削除された!
クラウドサービス(オンラインストレージを含む)に関する2つの危険性!
1. 危険性①:「契約アカウント」に関する危険性(不正アクセス)
2. 危険性②:「保存データ」に関する危険性(データ消失)
「個人アカウント」でもやっておくべき2つの対策
1.「個人アカウント」でも絶対にやっておくべき対策①:不正アクセス対策
2.「個人アカウント」でも絶対にやっておくべき対策②:2か所へのデータ保存
詳しくは、下記の動画ご参照ください。(講座動画時間:13分17秒)
みなさんこんにちは、スマホのコンシェルジュです。
今回は、「Googleでデータ消失!年金基金のデータが消えた理由と個人でもすべき安全対策」について説明して参ります。
豪州の年金基金のデータが消えた要因は、Google側の人為的なミスで発生したものになります。
但し、データ自体が消えてしまい、復旧までに1週間かかったという事件になります。
また、そのデータ復旧にGoogle以外のバックアップデータが活用され、最終的に1週間で復旧する事が出来たという事例でもあります。
この事件から、「Googleフォト」等に保存している写真やデータが安全なのか、個人でも出来る安全対策はあるのかについて一緒に確認していきましょう。
スマホのコンシェルジュの「YouTubeチャンネル」では、「スマホの基本操作」から「不具合時の対処方法」「スマホとパソコンの連携」等、スマホやパソコンに関する動画を多数配信しております。
是非そちらもご参照ください。
また、是非「チャンネル登録」もお願い致します。
【目次】
<1>データを保存する「オンラインストレージ」とは
1.データを保存する「オンラインストレージ」とは?(バックアップを含む)
2.「オンラインストレージ」の5つの特徴
3.「オンラインストレージ」の4つの危険性
<2>「オーストラリアの年金基金」で発生した「データ消失」の原因とは
1.「年金運用の契約者」がアカウントに1週間アクセス出来ない事件が発生!
2.原因は「人為的なミス」!「契約サービス」が自動的に削除された!
クラウドサービス(オンラインストレージを含む)に関する2つの危険性!
1.危険性①:「契約アカウント」に関する危険性(不正アクセス)
2.危険性②:「保存データ」に関する危険性(データ消失)
「個人アカウント」でもやっておくべき2つの対策
1.「個人アカウント」でも絶対にやっておくべき対策①:不正アクセス対策
2.「個人アカウント」でも絶対にやっておくべき対策②:2か所へのデータ保存
<1>データを保存する「オンラインストレージ」とは
それでは、まず初めに今回の事件の元となった「データを保存するオンラインストレージ」とはどのようなものなのかを簡単に確認していきましょう。
1. データを保存する「オンラインストレージ」とは?(バックアップを含む)
「オンラインストレージ」とは、インターネット上に「データ(写真や動画も含む)」を保存・保管するサービスになります。
「クラウドサービス」の一つでもあり、iPhoneであれば「iCloud」、Androidであれば、「Googleドライブ」「Googleフォト」が「オンラインストレージ」に該当します。
パソコンであれば「One Drive」や「Drop Box」も「オンラインストレージ」になり、スマホからも利用する事が出来ます。
2.「オンラインストレージ」の5つの特徴
それでは、次に「オンラインストレージ」の主な特徴についても一緒確認していきましょう。
「オンラインストレージ」の主な特徴は5つあります。
まず、一つ目は、インターネットに接続できる環境であれば、どこからでも接続可能で、どの機器からでも利用する事が出来ます。
二つ目は、特に特別な操作をしなくても、指定したフォルダーから利用している「オンラインストレージ」に自動的に保存する事も、自動的に同期させる事も出来ます。
三つ目は、「オンラインストレージ」から、直接、第三者に対して「データの共有」をする事が出来ます。
「メール」や「メッセージ」に写真や書類等を添付する必要がない為、通信量を抑える事が出来るという特徴があります。
四つ目は、データのバックアップ先としても利用する事が出来ます。
特にスマホで利用する場合が多いですが、端末内の主要なデータを「オンラインストレージ」に「バックアップ」として保存する事が出来ます。
端末の故障時や紛失時はもちろんですが、端末の買い替え時にも、データ移行の1手段として利用する事が出来ます。
五つ目は、「プライベート」であまり利用する機会は少ないかもしれませんが、「特定のデータ」を共同で編集したり、同時に作業する事が出来ます。
3.「オンラインストレージ」の4つの危険性
それでは、次に、「オンラインストレージ」の危険性についても一緒に確認していきましょう。
主な危険性は4つあります。
まず、一つ目は、「保存したデータ」が流出する危険性があります。
いつでも、どこからでも利用できるという事は、利用者以外の第三者にとっても同じで、利用しているアカウントにログインされてしまうと、同じデータを利用されてしまいます。
二つ目は、利用している「オンラインストレージ」に障害が発生した場合、「保存していたデータ」にアクセスする事が出来なくなります。
また、障害が復旧するまで、待つしかないという欠点があります。
三つ目は、「同期」に関連する問題が発生する場合があります。
特にパソコンの「One Drive」等でよく見られますが、「自動同期」を「オン」にしていると、「保存」を意図していない時でも勝手に「上書き保存」されてしまうという問題が発生します。
四つ目は、「保存したデータ」が消えてしまうという危険性が少なからずあります。
確率論的には非常に少ないですが、外生的な要因・人為的な要因で保存したデータが消えてしまう場合があります。
今回の年金基金の事件でも、「人為的な要因」にはなりますが、「保存していたデータ」が丸ごと消えてしまったという事実があります。
<2>「オーストラリアの年金基金」で発生した「データ消失」の原因とは
それでは、次に、「オンラインストレージ」に関連する事件として、「オーストラリアの年金基金」で発生した「データ消失」の詳細についても一緒確認していきましょう。
1.「年金運用の契約者」がアカウントに1週間アクセス出来ない事件が発生!
今回の事件の概要は、オーストラリアにある年金基金で、「契約者」が自分のアカウントにアクセスできないという事件が発生しました。
アクセス出来なかった期間は、2024年5月8日から5月16日までの1週間で、対象者の数は62万人になります。
皆さんもご存じのように年金基金は、基本的には「長期運用」を目的にした資産運用になりますので、1週間アクセスできなかった場合に発生する損失額がどの位になるのかは想像しづらいですが、それでも、数億円の損害賠償請求が発生する可能性がある事件になります。
2. 原因は「人為的なミス」!「契約サービス」が自動的に削除された!
オーストラリアの年金基金は、「Googleクラウド」を利用して、年金基金のサービスを契約者に対して提供していましたが、「Googleのオペレータ側の設定ミス」で、契約したサービスが自動的に削除されてしまい、関連するデータが消失してしまったという事件になります。
最終的には1週間で復旧することが出来ましたが、復旧に際して、利用していた「Googleクラウド以外のバックアップデータ」が利用されたという事実があります。
こちらで重要なポイントは、「人為的なミスにより契約していたサービスが自動的に削除されてしまった」という点と「Googleサービス以外のバックアップデータが復旧に活用された」という点になります。
いずれにしても、「契約しているサービス」以外の「バックアップデータ」も重要である事が浮き彫りになった事件でもあります。
クラウドサービス(オンラインストレージを含む)に関する2つの危険性!
それでは、次に「今回の事件」から想定できる「クラウドサービス(オンラインストレージを含む)」の2つの危険性について一緒に確認していきましょう。
1. 危険性①:「契約アカウント」に関する危険性(不正アクセス)
まず、一つ目の危険性は、クラウドサービスは「一つのアカウント」で、すべてが管理されている点になります。
その為、その「アカウント」が乗っ取られてしまうと、「保存している情報の抜き取り・削除」「サービスの停止」等、様々な危険性に繋がる可能性があります。
この点については、「個人」も同様で、「アカウント」自体を乗っ取られないように「セキュリティ」を強化する事が一番の防衛策になります。
具体的には、「2段階認証」はもちろんですが、「重要なデータ」が入っている「フォルダ」へのアクセス権限やパスワード設定等を行う事も重要になります。
2. 危険性②:「保存データ」に関する危険性(データ消失)
二つ目の危険性は、「保存したデータ(バックアップデータを含む)」が消失するリスクが少なからずあるという事実になります。
「Googleフォト」「Googleドライブ」「iCloud」等は、「バックアップデータ」まで消えてしまうという可能性は限りなく少ないといえますが、利用する「クラウドサービス(オンラインストレージを含む)」によっては、「バックアップデータ」も消えてしまう事もありますので、その点は覚えておきましょう。
加えて、「Google」「Apple」のクラウドサービスでも、偶然性の連鎖による物理障害・自然災害等の外生的な要因・操作ミス等の人為的な要因も含めると、バックアップデータも含め、データ自体が消えてしまう可能性はゼロではないという事も覚えておきましょう。
いずれにしても、「消失したくない重要なデータ」がある場合には、1つの契約サービスに依存しない「バックアップ体制」を用意しておくのも一つの選択肢になります。
「個人アカウント」でもやっておくべき2つの対策
それでは、次に「個人のアカウント」でもやっておくべき2つの対策について一緒に確認していきましょう。
1.「個人アカウント」でも絶対にやっておくべき対策①:不正アクセス対策
まず、一つ目は、スマホで一番重要なアカウントである「Googleアカウント」「Appleのアカウント」で不正アクセスが行われないようにセキュリティを強化する必要があります。
出来る事としては、「2段階認証の設定」、複数の端末を利用している場合には「信頼できる端末の登録」「ログイン通知の設定」の3つになります。
利用している環境によって、利用できるセキュリティ強化の方法が異なりますので、適宜ご対応ください。
Googleアカウントの「2段階認証の設定方法」等について知りたい方は、こちらの動画をご参照ください。
動画説明ページ(概要欄)にも、リンク(URL)を掲載しておきます。
2.「個人アカウント」でも絶対にやっておくべき対策②:2か所へのデータ保存
二つ目は、スマホで撮影した「写真」の「バックアップ」に関する問題点とそれに関連する対策になります。
「Googleフォト」、設定次第では「iCloud写真」も同様ですが、写真や動画のバックアップが行われると端末内から「オリジナル写真」が削除されるようになっています。
この機能自体は、悪い機能ではなく、むしろ有益な機能になります。
その理由としては、端末ストレージの空き容量を増やしてくれます。
端末の空き容量が増えると端末への負荷が減り、端末がスムーズに動くようになります。
また、写真や動画を更に撮る事も出来ます。
唯一の欠点は、「クラウド(オンラインストレージ)」上にしか、「オリジナルデータ」が残っていない為、一つ目に説明したような「不正アクセス」や何らかの理由で「アカウントへアクセス」が出来なくなってしまった場合に「保存していたデータ」を取り戻す事が出来なくなってしまうという危険性があります。
また、確率論的には非常に少ないですが、「保存していたデータ」が消えてしまった場合の対処方法が何もないという点になります。
「最悪の事態」を想定した場合には、少なくも2か所に「オリジナルデータ」を保存している方が安全になります。
「オリジナルデータ」を保存しておく場所としては、「スマホ」でも、「パソコン」でも、「USBメモリー」や「SDカード」等でも問題ありません。
また、「別のクラウドサービス」に、データを保存しても問題ありません。
但し、2番目の保存先として一番安全性が高いのは、インターネットに接続しないで利用可能な「USBメモリ」「外付けSSDやHDD」「SDカード」になります。
くり返しになりますが、あくまで最大リスクを考慮した場合の万全なデータ保護の対策になります。
「クラウドサービス」と「インターネットへの接続不要なメモリー」への「バックアップ」が現時点で考えられる一番安全なデータの保存方法になります。
以上で「Googleでデータ消失!年金基金のデータが消えた理由と個人でもすべき安全対策」についての説明を終了致します。
宜しければ「チャンネル登録」をお願い致します。
また、「有料メンバーシップ」にてコンビニで印刷できるテキストの提供も行っております。
ご静聴、ありがとうございました。
「【注目の記事】iPhoneとAndroidはどちらが安全?「ロシア」「中国」へのアクセスで比較!」もご参照ください。
「【衝撃】企業の情報流出が過去最多!銀行口座開設・ローン・SIMスワップ詐欺に繋がる身分証明書も流出!」もご参照ください。
<指導実績>
三越伊勢丹(社員向け)・JTB(大説明会)・東急不動産(グランクレール)・第一生命(お客様向け)・包括支援センター(お客様向け)・ロータリークラブ(お客様向け)・永楽倶楽部(会員様向け)等でセミナー・講義指導を実施。
累計50,000人以上を指導 。
<講義動画作成ポイント>
個別指導・集団講座での指導実績を元に、わかりやすさに重点を置いた動画作成
その他の講義動画は下記の一覧をご参照ください。
<その他>
オンラインサポート(ライブ講座・ZOOM等でのオンライン指導)とオフラインサポート(出張指導・セミナー形式のオフライン指導)も実施中。詳しくはメールにてお問い合わせください。
【全店共通】
03-5324-2664
(受付時間:平日10時~18時)